
- 業務効率化の第四歩:「その手作業、もう限界では?」基幹システム連携で実現する未来の働き方
業務効率化の第四歩:「その手作業、もう限界では?」基幹システム連携で実現する未来の働き方
1章 散在する情報から価値ある情報へ:これまでの振り返り
これまで3回にわたり、システム連携の旅路を歩んできました。
第一弾では、ばらばらのシステムが引き起こす手作業の疲弊という課題を提起し、第二弾では、それを解決するAPI、ODBC、ファイル連携といった具体的な方法をご紹介しました。
そして第三弾では、多くのプロジェクトが失敗する理由と、それを回避するための明確な目的設定、現場の巻き込み、導入後の運用計画の重要性を強調しました。
今回は、これまでの内容を踏まえ、基幹システムと他のシステムを連携させた具体的な事例についてご紹介します。理論だけでなく、実践的なイメージを持つことで、貴社のシステム連携の第一歩がより明確になるでしょう。
2章 なぜ基幹システムとの連携が重要なのか
日々の業務で「この情報をAシステムからBシステムに手で入力し直す作業、もうやめたい…」と感じたことはありませんか?その手作業は、時間とコストを浪費するだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも常に伴います。企業の心臓部とも言える基幹システム(ERP、販売管理、生産管理、会計システムなど)しかし、基幹システム単体では、すべての業務を網羅することは困難です。
顧客情報や売上情報が入力されていても、それらが他のシステムと連携していなければ、せっかくのデータも「宝の持ち腐れ」です。
例えば、顧客とのやり取りはSFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)で行われ、マーケティング活動はMA(マーケティングオートメーション)ツールで行われます。これらのシステムが基幹システムと連携していない場合、それぞれのデータが分断され、顧客の購買履歴や行動パターンを横断的に分析することができません。
基幹システムと外部システムを連携させることで、これまで見えなかったビジネスの全体像を把握できるようになります。これにより、より迅速な経営判断や、顧客一人ひとりに合わせたサービス提供が可能となり、競争力を飛躍的に向上させることができるのです。
3章 ベンダーのソリューションを活用する:効果的な連携の具体例
システム連携を成功させるためには、自社の課題を深く理解し、適切なソリューションを提案してくれるパートナーの存在が不可欠です。例えば、私たちのようなシステム開発ベンダーは、様々な製品やサービスを組み合わせて、お客様に最適なソリューションを提供しています。
ここでは、弊社サービスも交えて具体的な連携例をご紹介します。
業務例1:受注・在庫管理業務
奉行シリーズとECサイト、入出荷システムの連携
- 課題:ECサイトで受注した情報を販売管理システムに手入力し、在庫情報を生産管理システムに確認するといった非効率な作業。手入力ミスや、リアルタイムでない情報による販売機会の損失が発生。
- 連携効果:
奉行シリーズの販売管理システム(商蔵奉行クラウド)と、ECサイトや入出荷検品システム(入出荷検品NAVI)を連携させることで、業務効率は飛躍的に向上します
- ECサイトの受注情報が、自動で販売管理システムに登録されます。
- 顧客にリアルタイムで正確な在庫状況を提示できるため、販売機会の損失を防げます。
- 受注状況が自動で生産管理システムに反映され、生産計画の最適化に繋がります。
- 手入力によるミスをなくし、受注から出荷までのプロセス全体を効率化します。
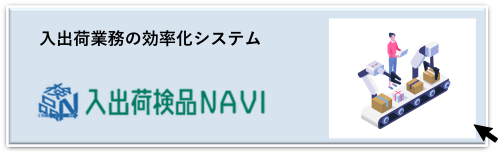
業務例2:顧客管理・マーケティング業務
ローコード・ノーコードツールを活用した連携
サイボウズ社の「Kintone」やSCSK社の「CELF」といったローコード・ノーコードツールは様々な基幹システムとAPI連携ができることも大きな特徴です。これらのツールを基幹システムと連携させることで、現場の個別業務に合わせた最適なアプリを迅速に開発し、基幹システムをより使いやすくすることができます。
- 課題: 顧客情報が営業、マーケティング、カスタマーサポートなど複数の部署で分断されており、顧客の行動履歴や購買パターンを総合的に把握できない。
- 連携効果:
- KintoneやCELFで作成した顧客管理アプリと基幹システムを連携させることで、営業担当者が外出先からでも最新の顧客情報や在庫情報を確認できるようになり、顧客対応のスピードと質が向上します。
- 顧客の問い合わせ履歴やWebサイトでの行動が、営業担当者も確認できるようになり、顧客対応の質が向上します。

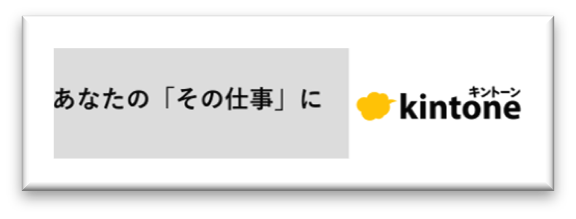
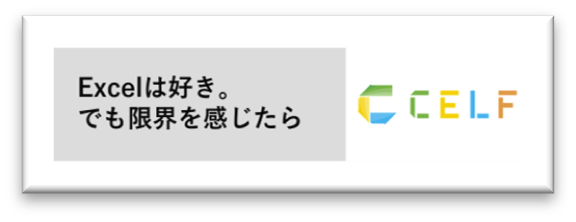
4章 成功事例から学ぶ「連携の力」
ある製造業の企業では、以前は受注から生産、出荷、請求までのプロセスが複数のシステムに分断されており、部門間の情報共有に時間がかかっていました。
そこで、販売管理システム、生産管理システム、会計システムをAPIで連携させ、データの自動連携を実現しました。その結果、以下のような大きな成果が得られました。
- リードタイムの短縮: 受注から出荷までのリードタイムが30%短縮。
- 在庫の適正化: リアルタイムな在庫情報に基づいて生産計画を最適化し、過剰在庫と欠品を削減。
- 業務効率の向上: 請求業務にかかる時間が月間で約50時間削減され、経理部門が戦略的な業務に集中できるようになった。
このように、システム連携は単なる効率化だけでなく、ビジネスプロセス全体の最適化と、それに伴う企業の競争力向上に直結するのです。
5章 次のステップへ:貴社の連携プロジェクトを成功させるために
システム連携は、単なる技術的な課題解決ではなく、企業の成長を加速させるための戦略的な投資です。
今回のコラムでご紹介した業務例を参考に、まずは貴社の中で最も非効率だと感じている業務や、情報が分断されていると感じる業務から検討を始めてみてはいかがでしょうか。
「なぜ連携するのか」という目的を明確にし、現場の課題を洗い出し、適切なパートナーを選定する。これまでのコラムで解説してきたこれらのステップを丁寧に踏むことで、貴社のシステム連携プロジェクトは必ずや成功へと導かれるでしょう。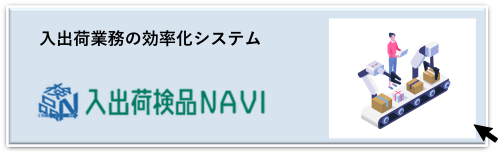
次回の最終回では、システム連携の導入後、さらにビジネスを加速させるための展望について解説していきます。
業務効率化の最終章:未来へ続く、データ駆動型経営


